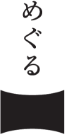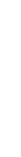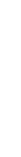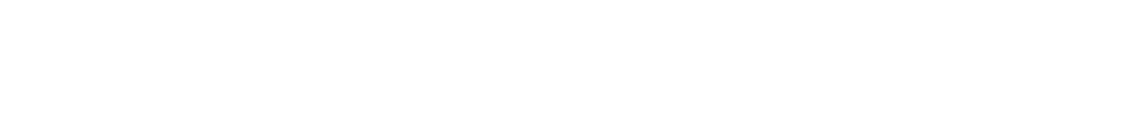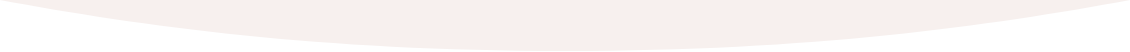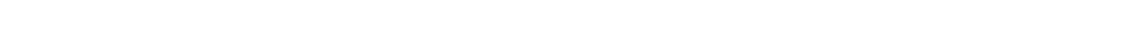めぐるの最新情報(ニュース)
10月、ウルシの木も葉っぱが黄色に色づきはじめ、実も茶色に枯れてきました。この実にはロウ分が含まれていて、かつては和蝋燭の原料になりました。漆とろうそく、会津藩を支えた二つの産業がこの木からもたらされました。

さて、1ヶ月ほど時計を巻き戻して・・・9月に入ってからは、めぐるの漆塗りは「下地」という工程に入りました。

「水平」の漆塗りを担当いただいているのは吉田徹さん。最適な材料と工程を吟味し、漆の力をまっすぐに引き出すことに定評があります。正統的な漆塗りでは会津で一番と言われる塗師さんです。

下地の工程では、漆に土の粉などを混ぜ合わせてペーストを作り、何度も塗り重ねていきます。完成したら外からは見えなくなってしまう部分ですが、木地と漆塗りの間に、この下地が丁寧に施してあることで、人間で例えるとそれが筋肉の役割を果たして、長く使ってもへこたれない丈夫な器となる大事な工程です。

こちらが、下地に使われる地の粉(じのこ)、珪藻土を焼いたものです。多孔質で、非常に細かく、サラサラした粉です。

上の地の粉と混ぜるのが、こちらの糊漆。米糊と漆を混ぜたものです。

ちなみに下の写真がなにも混ぜていない生漆(きうるし)です。生漆と比べると、上の糊漆の方がもったりと粘度が高い感じがすると思います。

下地の作り方も毎回同じではなく、その時の天候や漆の質によって、その配合を変えていきます。
吉田さんは簡単に下地を付けていますが、柔らかいペースト状の下地を素地のかたちを崩さずに均一に塗っていくのは、熟練の技があってこそです。
制作の様子は、今回もこちらの動画からたっぷりとご覧ください!下地は何故大切なのか、吉田さんによる解説もお聞きいただけます。