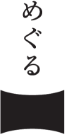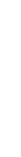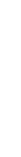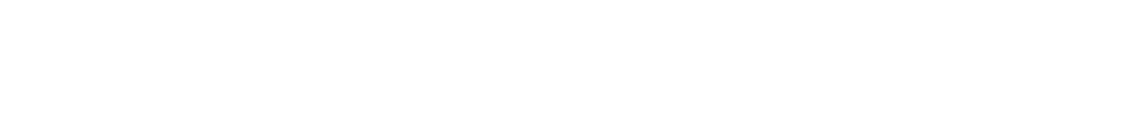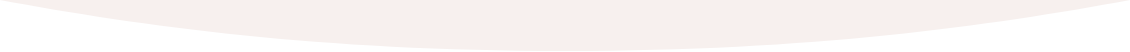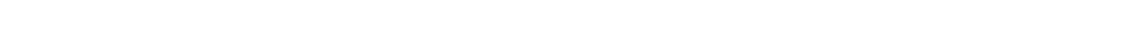めぐるの最新情報(ニュース)
今回の制作工程動画はこちらになります。是非ご覧いただけましたら幸いです。
夏に入る頃になると、「めぐる」制作の主役も木地師さんから塗師さんへ交代しました。
水平の器の漆塗りを担当いただいているのは吉田漆工房・三代目の吉田徹さん。最適な材料と工程を吟味し、漆の力をまっすぐに引き出す確かな技に定評があります。

さて、「漆塗り」と聞くと、皆さん、木に漆を塗り重ねているイメージを持っていらっしゃる方が多いと思います。
でも、木と漆の間に、とっても大事な部分が隠されています。
それが、今回の工程である「下地(したじ)」です。
漆塗りではまず、木地に生漆を吸い込ませる「木固め(きがため)」という作業をした後で、「下地」の工程に入ります。

下地は、漆に珪藻土(けいそうど)を焼いた粉などを混ぜ合わせてペーストを作り、何度も塗り重ねていきます。
それが器の強度を高めクッションの役割を果たすので、長く使っても痛みが少ない丈夫な器になっていく秘密です。

下地を付ける時に使うヘラも、ヒノキやマユミの木から塗師さんが自分で削り出して作っています。
器の種類やかたちに合わせて、その都度調整しながら使っていきます。道具づくりも職人さんの大切な仕事のひとつです。
下地についてのさらに詳しい内容は、昨年の動画になりますが、今回の続きの工程をしながら、吉田さんに分かりやすい解説をしていただいています。よろしければ、こちらの動画もご覧ください。